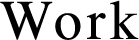


全員で考え、全員でつくる
革新は、無数の連携から生まれる
シグマの製品開発には、本社と会津工場の、技術者同士の緊密な連携が欠かせません。あらゆる部門・職種の社員が無数のやり取りを行いながら、革新的な製品をつくるという一つの目標に向かって進んでいきます。このページでは、そのような複雑なつながりの一部を図にまとめており、シグマならではのものづくりの進め方について解説しています。

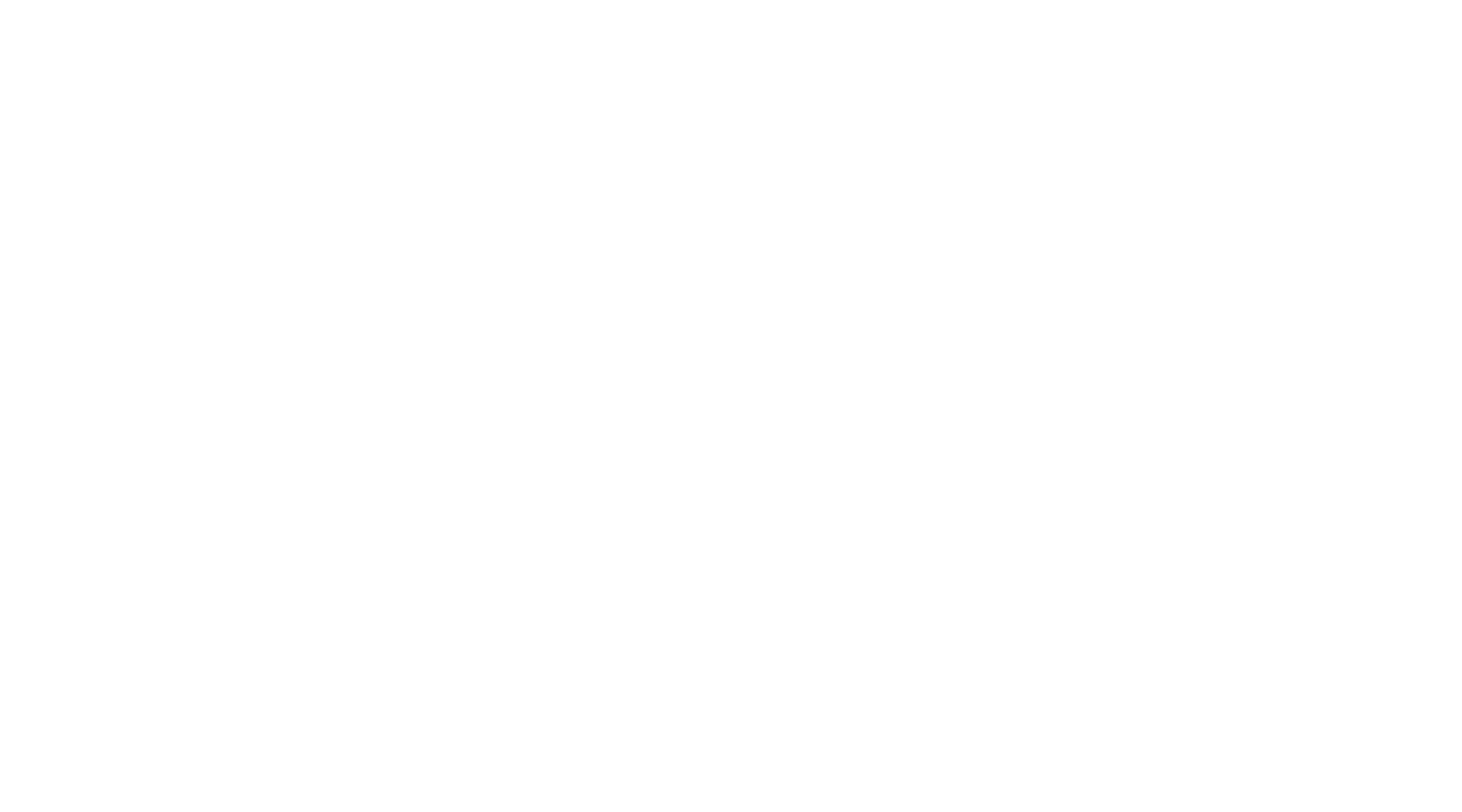
製品の企画をもとに、担当する設計者が「その製品は成立するか」「どのような性能で実現できそうか」を検討します。レンズは光学設計から、カメラは主に機構設計と電子回路設計から検討が始まり、工場の生産技術とも情報を共有しながら進めます。その際、設計者からの逆提案により、企画の一部が変更になることも珍しくありません。こうして製品スペックの大枠が固まり、本格的に開発プロジェクトが動き出します。
製品の開発プロジェクトが本格化し、開発各部門の設計者が、担当するそれぞれの分野で設計を進めます。これと並行して、工場の技術部門は試作に向けた準備や量産性の検証、量産段階で用いる金型や治工具の設計を行います。この段階で、設計者からの提案により製品に機能が追加されたり、仕様の一部が変更になったりすることが多くあります。
設計がある程度仕上がると、生産技術など工場の各部門と連携して試作を行います。生産技術と機構設計の担当者が組み上げた試作品をもとに問題点を洗い出し、設計内容を改善していきます。最終的には、製造ラインで組み上げた試作品を検証し、目標とする性能や精度を満たしていることが確認できれば、量産段階へと進みます。
発売に向けたスケジュールが決まり、工場の製造各部門による量産が開始されます。生産技術や治工具設計の担当者は、量産が円滑に行えるよう製造現場をフォロー。トラブルが発生した際は、速やかに対策を検討します。この段階になると、各部門の設計者は次の機種の初期検討や設計を並行して進めていきます。