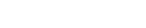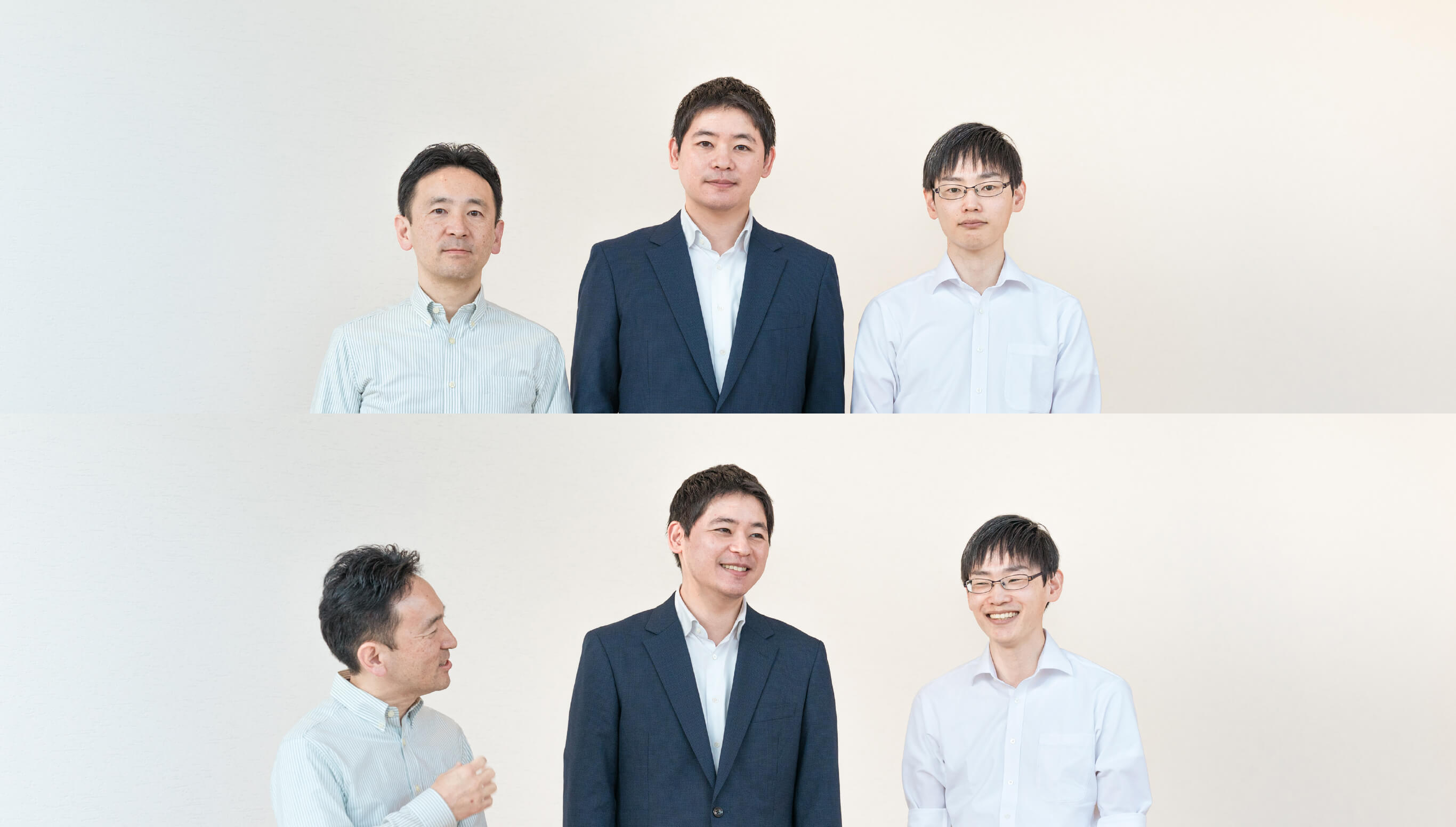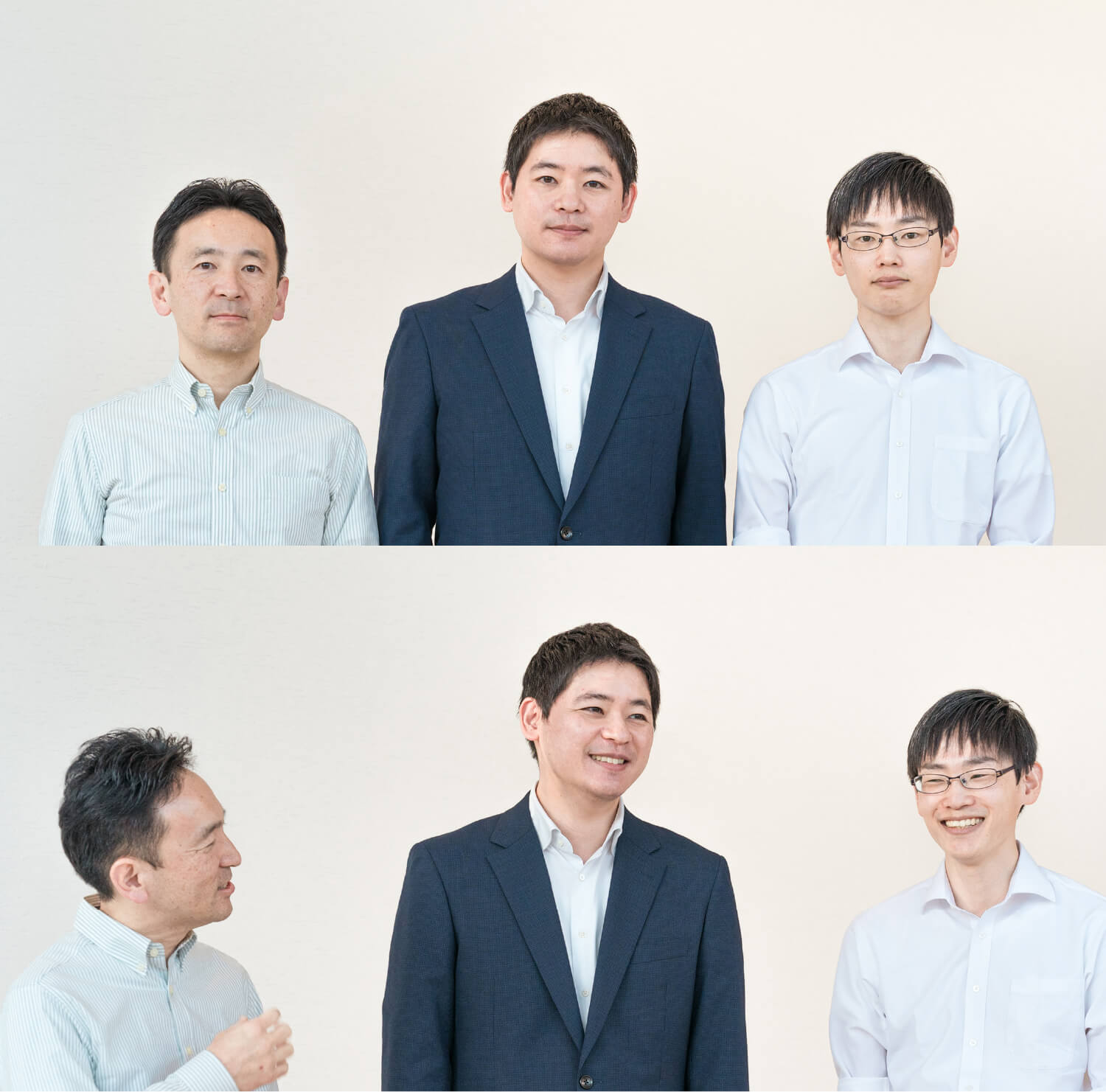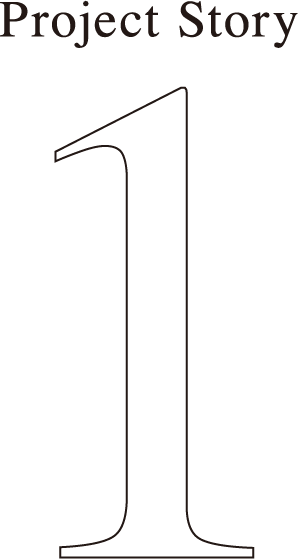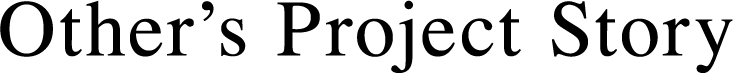毎日1〜2時間の「ワイガヤ」
シグマにとってのかっこよさとは?
- 門倉
- 当時のカメラ市場はフルサイズミラーレスカメラの黎明期で、シグマとしてもフルサイズのカメラと、そのためのレンズを開発することが決まっていました。その中の一つとして、「45mm F2.8 DG DN |Contemporary」のレンズ開発はスタートしました。先行して開発が進んでいたカメラ「SIGMA fp」のキットレンズになることも想定されていた製品です。
- 関
- 社長からは「とにかくかっこいいものをつくろう」という話があったのを覚えています。どうやって特徴ある製品にしようかと悩み、門倉さんとはああでもないこうでもないと毎日のように話しあっていましたね。
- 門倉
- その当時、関さんとは毎朝1~2時間、雑談をすることが日課になっていました。担当業務についてはもちろん、もっと広い視点でカメラ業界について、シグマの強みについて。その中で今回の製品がどうあるべきかを話し合いました。ミーティングという堅苦しいものではなく、あくまで「ワイワイガヤガヤ」と。
- 関
- いわゆる「ワイガヤ」ですね。話題は私から持ちかけることが多いですが、門倉さんと一緒に同じ話題について考え、お互いの意見をぶつけ合います。ときどき思いもよらない回答が返ってくるので、楽しくなってきて、ついつい1時間でも2時間でも話し込んでしまう(笑)。そこで必ず話題にするのは、「お客様に本当に喜んでいただけるのか?」という話。このときもそこを徹底的に話し合い、目指す方向性を模索しました。
- 門倉
- お互いに会話を楽しんでいる感じでしたね。「かっこいい」の捉え方は人によって全然感じ方が違うというのが発見でした。例えば、私はエレガントな車がかっこいいと思っていますが、関さんは無骨な車がかっこいいと。当時は、帰り道でよくその日のワイガヤについて振り返っていましたね。「自分はなぜあの車を選んだんだろう?」「何百万円もなぜ払おうと思ったのかな?」そして、「かっこいいレンズってどんなものだろう?」と。
- 関
- そこから、「『自分たちにとってのかっこいい』ではなく、『シグマにとってのかっこいい』『シグマユーザーにとってのかっこいい』ってなんだろう?」と突き詰めていきました。コンセプトとしては、他社と差別化しつつ、「これこそシグマの製品だよね」と言われ、「お客様がこの製品を持っている事を自慢できる」ものをつくりたい。
そう考えたとき、会津工場の技術力を全面に押し出すような製品をつくれば、「シグマのかっこいい」が表現できると考えました。緻密で、精密で、愚直。そんなものづくりの姿勢が具現化されたような製品。そこをコンセプトにしました。うちでつくれる最高のもの、最高の質感と感触。そこを追求すれば、差別化にもなるし、「シグマのかっこいい」になる。10年、15年経っても色あせないかっこよさが提示でき、お客様も喜んでいただけるのではないかと考えました。
自分たちのこだわりを提案する
- 門倉
- そのようなコンセプトに基づいて設計に取り掛かりました。日々の計画図を見ながらワイガヤを繰り返し、ある程度の完成度になった段階で、3Dプリンターを使ってモックを作りました。思い返せば、いわゆるコンセプトモックだったと思います。
- 関
- そんな矢先に、社長から声をかけられたんです。開発中のミラーレスカメラ「SIGMA fp」に合わせるレンズを見せてほしいと。そこでモックを見てもらったところ、「これおもしろいじゃん!」となり、企画会議で検討することになったんです。門倉さんが、心に響くコンセプトモックを作ってくれていたおかげです。ワイガヤで絞り出すように出したコンセプトがやはり良かったんです。
- 門倉
- 社長の反応がすごかったのを今でも覚えています。社長がすぐに企画会議の議題に上げて、その日の内に方向性を再検討するという話になりました。
- 関
- 議論の末、最終的にはこの案の方向で進めることに決まりました。コンセプトモックが、「かっこいいものをつくろう」という当初の方針とも合致していたことで認めてもらえたんだと思います。
会津工場の技術にフォーカスした、
唯一無二の製品へ
- 関
- このようにしてコンセプトをまとめ上げ、高い加工精度と外観品質を活かした、会津工場だからこそ実現可能な製品を目指しました。最初は、「なんでこんなにお金かけるの?」「技術的にかなり難しいけど、そこまでする必要性は?」という反応が多かったです。でも、各パーツが組み上がった状態を見てもらうと、一気に前のめりになってくれました。「こういうことがしたかったのか!」「こんなレンズ見たことない!」と。
- 門倉
- 作り上げるまでは本当に困難の連続でしたね。特に難しかったのは、操作時の感触をつくり込むことです。グリスを調整して実現したほどよいトルク、しっとりと吸いつくような操作感には特にこだわりました。あと、絞りリングのクリック音にもこだわっています。音量も音質も徹底的にテストしました。音が大きいと品位を損ねるし、小さすぎると物足りない。中間のちょうどいいところを追求して仕上げています。いずれも生産技術の担当者と協力して作業を進めていきました。実際に試作品を触りながら、ああでもないこうでもないと。最終的に狙い通りの感触にたどり着き、社長にも驚かれるくらいの品質にできました。
- 門倉
- 当時の品質保証部の部長からも驚かれまして、「うちでこんなのつくれるのか!?」とものすごく褒められましたね。
- 関
- その方はもともと生産技術部門にいたので、加工についても組立についてもとても詳しい人です。だからこそ「これをうちでつくったの!?」という驚きが大きかったみたいで、嬉しかったですね。
コンセプトレンズがシリーズ化、
次の新しいチャレンジへ
- 関
- 発売してからの反響も大きかったですね。
- 門倉
- ある雑誌の企画で、その1年間で販売したものの中から一番いいレンズを投票で決めるというイベントがあったのですが、なんと1位に選出されたんです。「このレンズは飛び抜けて個性的」という選評もありました。
- 関
- 購入されたお客様の満足度も非常に高かったです。社長もこのコンセプトを気に入ってくれたのか、同じコンセプトでどんどんレンズを増やしてシリーズ化しましょうという話になりました。それで、2機種目から「I series」を冠するようになったんです。1本目の開発時点では、シリーズ化しようという話はありませんでしたね。
- 小北
- 2機種目から私も参加しました。「I series」の開発は、社内でこれまで経験のないことにチャレンジしていく仕事だと捉えています。前例がないケースが多く、試行錯誤することにやりがいを感じています。
- 関
- 小北さんには、2機種目以降で新たに付属することに決定した「マグネット式メタルキャップ」と、そのキャップ用のホルダーを担当してもらいました。実は、業界的にも珍しい試みです。このときも、「どんなキャップがかっこいい?」「どうしたらシグマらしさが出る?」とワイガヤを3人で毎日行いました。最終的に、時間がない中でも小北さんが仕上げてくれて、個性的なキャップとホルダーを投入することができました。
- 小北
- 前例のないアクセサリーでしたし、私自身の開発経験も浅かったので、最初は戸惑いました。それでも必死に食らいつき、胸を張れる仕事をすることができたかなと思います。今後は、さらにユーザーの目線に立って製品を開発していきたいと思っています。関さんや門倉さんの仕事をすぐ近くで見てきたなかで、より強く意識するようになりました。
- 門倉
- 私は、この製品の開発が終わってからもずっと思っていますが、「I series」の満足度を超える製品をつくりたいですね。全く別の方向性で。そういう野心を胸に日々の仕事に取り組んでいます。
- 関
- 今はもう「I series」の開発は多くの部分を若手に任せています。私みたいなベテランはサポート役に回り、若手にどんどん経験を積んでもらうのが組織運営の理想だと思うので。私が願うのは、若い人たちが製品の開発にあたり、仕事に対して自らストーリーを紡ぎ、製品開発のみならず自分の人生についても思い描く世界をつくり出してくれるようになること。そういう人を1人でも多く育てられたら、最高に嬉しいですね。